中小・零細企業経営者のための意思決定サポート
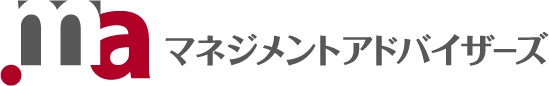
〒250-0405 神奈川県足柄下郡箱根町大平台419
営業時間 |
|
|---|
お気軽にお問合せください
お問合せはこちら
お役立ち情報
中小企業金融円滑化法の終了期限について

2013.03.05
2013年3月31日をもって中小企業金融円滑化法の再延長期限を迎えます。
この先の延長はもう無い事が確定しています。
日本全体がデフレ不景気の中であえいでいた時期に、当時亀井静香金融相(当時)の肝いりで生まれたこの法律。
正直、悪法だったかか善法だったかは今では意見の別れるところです。
その時点で市場から退席すべき企業が生き残り、結果として不景気デフレを助長した部分があるというのが主なる見解です。
各種新聞の金融・財政関連面では記事にたびたび載っています。
この法律によって金融機関に条件変更などを行った利用者の95%以上は中小企業です。
2009年12月に緊急施行されたこの法の下、申し出をした企業は、ほぼ全社借入金の返済負担を大幅に緩和することができました。
金融機関から借入金返済猶予をしてもらえた企業の中には「倒産」の憂き目に遭わないで済んだところも多くあります。
また、当時金融円滑化法を利用し返済条件を変更した企業にはある条件が付けられました。
「経営改善計画書」の提出です。
この青写真のもと、業績を回復する(返済能力を回復する)ことが求められました。
計画に対し80%の達成を促されてきました。
ところがです・・・・
この法律の延長期限が訪れることによって、この判断がより正確になされるようになると推測されるのです。
どうしてでしょう・・・?
実抜計画(実現可能な抜本的改革)を達成するために経営改善計画書を提出している企業は意外に多くありません。
書面ではなく、口頭で金融機関担当者にヒヤリングされ、その内容を担当者が代わりに文書にしている場合が多数あるのです。
すなわち自分で考え、書面にし、改めて行動に移す、といった原則的な経営活動が行われていない状況があるのです。
今まではそれがまかり通ることがありました。
しかし4/1以降からはそうはいきません。
貸出金の条件変更などを受けた企業は、今後前述の資料等を明確に提出しないと「格付け」に影響されることとなります。
金融機関の自己査定に影響するのです。
当局は金融円滑化法終了後も金融機関には同じスタンスで企業に相対するよう求めていますが、それは表向きとしか理解できません。
なぜならば、「格付け」が同じスタンスではなくなるのですから所詮無理な話なのです。
不良債権(もしくはそれに準ずる債権)は金融機関にとっては必然的にコストがかかります。
今まで強引に正常債権と見ていた時期に比べ10倍近くのコストがかかってしまいます。
いや現実にはそれ以上でしょう。
それを思えば金融機関の判断は厳しくなるのは当然なのです。
金融機関自体がつぶれては元も子もありませんから。
円滑化法終了後に返済期限(更新期限)を迎える利用先はそれ相当の準備をしていないと、これからは渉り合えなくなります。
「うちは利用してないから・・・」
大丈夫でしょうか・・?
お取引先の企業が利用していたら、そのあおりを受ける時期も考えないといけません。
無関心ではいけない、ということです。
新聞記事は比較的楽観的な記載が多いですが、現実は厳しい。
そうとらえておく必要がありそうです。
本日はこの辺で・・・
無借金経営と実質無借金経営

2010.9.25 無借金経営と実質無借金経営
このところMA(経営意思決定)アドバイザリーで話題になることがあります。
無借金経営とは・・・ということです。
書いて字のごとく「借金がない経営」ということですね。
狭義の意味では「金融機関からお金を借りていない」ということで使われています。
だが、実際無借金経営というのは有り得ない話なのです。
なぜでしょう・・・?
それは企業を経営する中での借金は、申し少し言い方を変えれば「負債」のことを指します。
従って貸借対照表にある流動負債・固定負債の項目ということです。
これすべて借金なわけです。
支払手形・買掛金・短期借入金・未払金・長期借入金等です。
またもっと解釈を広げれば、人件費も後払いである以上買掛金(負債)の性格と同じなのです。
したがって企業はどの日で区切ったとしても、無借金状態は有り得ません。
貸借対照表の貸方の項目が(負債項目が無く)純資産だけという企業でないといけないからです。
結果で言えばどこを探しても無いのです。
一方で、「実質無借金経営」という言葉が使われることがあります。
これはどういうことでしょう・・・?
借金をしていても、常にその額以上に現預金が多いことを意味しているのです。
銀行借り入れ 1億円 < 現預金 2億円
こういった場合でしょう。
なお、これは断片的な状態ではなく、常にこういう状態でないといけません。
月のいつをとっても、年のいつをとっても、ということです。
また上記の記載にあるとおり、広義の意味では貸借対照表の負債項目を現預金が上回っている状態ということになるでしょう。
正直、こんな企業はなかなか無いのですが・・・。
なので一般的には、便宜上、銀行借り入れ<現預金、の状態を事実上無借金経営とか実質無借金経営と言うのです。
この特徴は・・・・といえば、これに尽きます。
毎年結果的に黒字で大変な納税をする羽目になる、ということです。
上場企業には許されても中小零細企業には真似のできない大技ですね。
実質無借金経営の響きは素晴らしいが、継続は並大抵のことではないということになるわけです。
答えを知るよりプロセスを知る
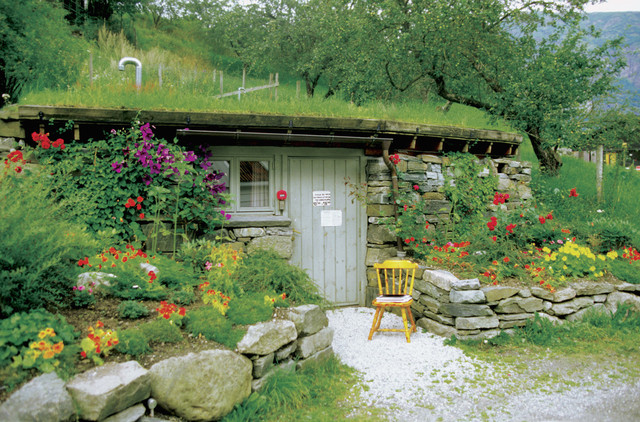
2009.05.21 答えを知るよりプロセスを知る
誰もがわかっていること・・・
それは言い換えれば「答えが分かっていること」でもあります。
算数で表現すると1+1=2であったり2×3=6であったりします。
この答えはいくつあるのかといえば、それはたったひとつでしかありません。
計算式を与えられ演算する、ことにおいては「間違い」はないものです。
正誤のはっきりする問題とはこういうものを指します。
その一方で、正解が見つからないもの(見つけにくいもの)もあります。
どういう問題なのでしょう・・・?
それは「答え」だけが決まっている問題です。
「結果10になる計算式は・・・?」と問われればいくつもの計算式が思い浮かぶことと思います
5+5、2+8、10×1、30÷3などなど、その数たるや多いですね
結論が決まっていることに対し、その過程を探ることが一番難しいのです。
これは世の中すべての問題に当てはまるはずでしょう。
誰かが5+5が正解と考えた場合、どうしても2×5とは考えにくくなってしまうのです。
これがコンフリクト(葛藤)の原因のひとつではないかと感じます・・・
むろん、すべてが5+5の答えで統一されてしまうような場合、およそ自由発想な組織とはかけ離れてしまいます。
国家で言えば「北朝鮮」のような著しく偏ったものになるのですね。
国家でなくとも企業などの組織、仕事仲間などでもまったく同じです。
- 見方はいくつあっても良い。
- そのほうがいろいろな可能性が見出せる。
- 視界が広くなる。
- 効率的な手法が導き出せるかもしれない。
結局、結果を知る(見る)より、結果にどう結びつける(た)かが問題なのである、ということであるとおもいます。
金融機関との融資のリスケジュール交渉に当たって

2008.11.15 金融機関との融資のリスケジュール交渉に当たって
企業の資金繰りについて相談を受る機会が多いこの頃です。
「現在借りている銀行融資の毎月の返済額を変更(大幅減少)してもらいたい」
まさしく約定変更、リスケジュール(金融機関による債務支援)のことです。
(これにより資金繰りが大幅に整えることが可能となる反面、新規融資は受けられなくなる)
相談された者は、安易に出来るものだと合点していました
必要遺書類を整えればOK、という程度で考えていたのでしょう。
「それでは無理です」と応えたところ・・・
かなり語気を荒げ「なぜだ!」と食い付いてこられました。
これは間違いなのです。
しかも大きな間違いですね。
そもそも金融機関は資金を貸したことでは収益は生まれません。
無事回収したことで初めて収益が生まれるわけです。
5年なら5年、3年なら3年の間に生まれるであろう利子を受け取り、元本の償還を受けなければならなりません。
そもそも「この予定を壊してくれ」という依頼なのです
金融機関はボランティア団体ではなく営利団体です。(信金などは半非営利であるが、基本は同じ)
すなわち「利益の追求」をしなければなりません。
安全に回収し、利益を得ることに関してはそれこそ命題なんですね。
それを一旦金銭消費貸借契約で融資を受けた側は、いくら資金繰りがきつくなったからといって半ば事務的にリスケ出来ると判断してしまうのは虫が良すぎるわけです。
個人的に金融機関出身だから書くのではありません。
そもそも彼らは「時間がない」のです。
そのなかで上からは成績を求められています。
小さな利益より大きな利益を自然と追求してしまうのです。
つまり、返済条件の変更手続き稟議より新規案件稟議に力が入ってしまうのですね。
中小零細企業の支援とはいえ、儲け話ではないものには反応が鈍くなるのは当たり前でもあるのです。
そこを曲げて依頼するのですから、並大抵の意気込みでは実現が難しいわけです。
世間ではよく「リスケ、リスケ」と口にする場面が多いです。
しかし実はそれ相当の注力によってでなければ実現は難しいことを忘れてはいけません。
そのたびに事務的に融資担当者が動くわけがありません。
なんだかんだ言っては乗り気にならない担当者を責めるより、まずは「何を依頼しようとしているか?」を再確認することが先決です。
「生産性のないことを優先してくれ」と依頼しているのですから。
繰り返しますが、金融機関の肩を持つ気はさらさらありません。
そうではなく、出発点は「無理な注文である」という認識なのです。
間違っても「手前勝手な依頼」でもあることを失念しないで交渉して欲しいと思います。
そのうえで「動く(債務支援の)必要性」を彼らに抱かせること・・・
これがまさにリスケジュールの肝なのです。
「心が伝わる」ことこそ、実現する(債務支援に前向きになる)一番の近道となるでしょう。
成果主義という「理念」

2008.08.23 成果主義という「理念」
「我が社は成果主義だから」 と、言われたとします。社員はどう受け止めるでしょうか・・・?
「出来るヤツはいいよな・・・」
「また競争させるのかよ・・・」
「それ以外にも評価あるだろ・・・」
「よしゃ、やったるぞ!」
とまぁ、こんな印象を持つ社員がきっと多いはずです。
当然のことだと思います。
なぜならそういう印象を持ってもらうべく発言しているからです。
言い換えれば「結果が全て」と言われているのですね。
私だったら・・・・そう、こういう会社には勤めません
なぜでしょうか・・・?
会社側としては・・・
「やる気のない社員を振り落とす」
「それぞれの潜在能力を引っ張り出す」
といった狙いを持つことが出来ます。
確かに間違ってはいません。
しかしこの手法は、通年そして会社の理念として持つには、ちょっと違和感が残るんですね。ましてや経営陣が外に向けて「我が社は成果主義です」なんて言ってはいけません。
なぜ・・・?
簡単に言えば、それは「足元」ばかりを見過ぎているということの裏返し、なのです。
ゴールが見えている時のラストスパートのような状況ならOKかもしれません。
ゴールすれば、ひとまず終わるのですから。
しかし、会社には実際にゴールはあるのでしょうか・・・?
そう、ないのですね。
常に前進あるのみ、そして結果を出したとしてもさらに結果を求められる場合もります。
つまり・・・・結果を評価する仕組みでは「次がない」ということを再認識する必要があるわけです。
成果を得やすい仕事をしてしまい、「仕込む」ことが無くなってしまう。
単純に、結果を出しているほうが評価が上がるのです。
この結果、数年もすれば状況が激変します。
もともとその市場が多きければ良いが、そうでもない場合、荒れ地で成果を探す、ことになってしまうのです。
(もっとも大きな市場は大企業が寡占するので、中小零細企業にとっての市場のサイズはもともと大きくはない)
古の狩猟民族や現在でもなお狩猟を主に行なっている部族などでは、獲物を得る掟といったものがある場合が多いようです。
「まだ小さなものは捕らないでおく」
「種を絶やさないよう、繁殖に影響の少ないものを捕る」
等々、現在のビジネスに置き換えれば非常に判りやすい掟ではないでしょうか?。
この原理・哲学を援用すれば、成果主義とはいかにも非合理な考え方である、と言わざるを得ません。
「取るだけ取っちゃえ・・・・」
この哲学は、イージーで浅いものだと気がつきます
そうあくまでこれはスポットの戦略でしかないのですね。
経営者が理念として声高に言えば、場合によっては倫理的にNGとなるかもしれません。
事業計画とは・・・

2008.04.11 事業計画とは・・・
よく「事業計画」という言葉を耳にします。
当然ですね。
経営者からの相談には不可欠なワードですから。
さてこの事業計画・・・どんなものでしょうか?
「事業を計画し、実行し、結果を得るためもの、そういった類ではないか」とその多くの返事が返ってきます。
当たらずとも遠からずといったところではないでしょうか。
どの経営者も事業計画、事業計画と口をそろえますが、ではいったい何をすれば良いのか・・・?が余り明確ではないのです。
これが大きな落とし穴なのです。
そもそも事業の継続は「資金繰り」によって成り立っています。
簡単に言えばお金がないと事業は出来ません。
壮大な事業計画というのも、実は地道な資金繰りがあるからこそ成り立っているわけです。
資金繰りが整わなければ、それは絵に描いた餅になってしまいます。
この点を経営者は忘れてはいけません
金融機関の融資担当も時には「事業計画」と誤った言葉を発するときがあります。
それは本当のところは資金繰りの事を指している、といった具合なのです。
短期の事業計画→短期の資金繰り
中期の事業計画→中期の資金繰り
この様に言っても過言ではありません。
「資金繰りを整えるためにどんな事業に取り組むのか」がまさに事業計画ということになります
私はそう思っています。
ちょっとした禅問答のようですが、いかがでしょうか・・・?
売掛金の買取らせ方式の資金調達は是か非か?

2007.12.22 売掛金の買取らせ方式の資金調達は是か非か?
ここに来て政府は中小企業支援対策のひとつとして、信用保証協会を利用した融資方法の検討に入った、と新聞記事に記載がありました。
具体的には「売掛金(債権)の買い取り」です。
(皆さんの企業から言えば「売掛金の売り」ということ)
記事を読んだ方はある程度理解できるはずです。
通常、融資を受けるに当たっては「保証人」もしくは「担保不動産」のとりつけが一般的ですね。
(ときに無担保・無保証人の取扱いもあり)
ところが最近ではなかなか保証人になってくれるという、ありがたい人間も少なくなりました。
不動産を担保設定して、という方法もベンチャー企業など不動産を持っていない経営者には使えません。
すでにメガバンクなどは優良企業に対し「売掛金」を担保にとり融資を行なっています。
これはあくまでも、「質権の設定」を行ない、「代理受領」をするカタチですので、買い取りとは違うことを念頭に置いてください。
(個々の対応では差はあり)
これによって、万が一返済が滞った場合、金融機関は「売掛金を回収する権利を執行するだけ」で良くなるわけです。
この方法、なかなか画期的ですが、残念ながら対中小零細企業では頻繁には行なわれていません。
なぜなら、(やや専門的ですが・・・)質権設定のための公正証書作成の手間・相手先の承諾が必要・信用調査の手間などがあるからです。
要は馴染みにくい状況なのですね。
そこで今回浮上したアイデアが、売掛金担保ではなく「売掛金の買い取り」なのです。
これはイメージでは「割引手形」によく似ています。
*割引手形・・・売掛金の回収に変え支払期日に記載金額を支払う旨の手形を受け取った企業が、金融機関に手数料を払い、その手形を買い取って貰うこと。
要するに、売掛金回収を手形受領というカタチではなく、「売掛金自体を保証協会を使って金融機関に買い取らせることで現金化する」を意味しています。
イメージで言えば「割引売掛金」ということです。
なかなかアイデアとしては面白いと思います。
企業としては、何よりも、手形商売をしていない先に売っても、その売掛金を金融機関に回せる(買い取らせる)ので、手っ取り早いのです。
これが広まれば確かに企業活動には大きな追い風となるかもしれません。
が、しかしです。
MA加藤はなかなかこの制度は、現実としては難しいのではないか、と考えます。
なぜならば、結局のところ融資を受ける企業のみならず、その先の企業をも信用調査する部分は売掛金担保融資と何ら変わらないからです。
直接資金を貸し付ける企業以上に、その先の企業の信用度に左右される結果になるのです。
判りやすく言えば、貸し付けを受ける企業が黒字でも、そして保証協会の保証が付いても、その先の企業が赤字であれば、利用が出来ないことになるということです。
単純に、一社飛ばししただけですね。
そんなことを連想すると、この制度も「付け焼き刃」のように思えてしまいます。
無論、ここで書ききるだけの簡単なアイデアだとは思っていませんが、それにしてもどーも「マユツバ」に感じてしまいます。
そんなところからも、この制度については、しばらく御上(おかみ)の様子を見守る必要があると思います。
従業員の退職金準備

2007.9.16 従業員の退職金準備
企業にとって経営資源は「人・もの・金・情報」と言われています。
まさにその通りなのですが、その「人」には役務にたいし「対価」が支払われます。
「報酬」であり、一般的には「給与」ですね。
これがあるから人は働くわけですし、その多寡によって頑張るモチベーションがあがったりするものです。
また、企業の業績によっては「賞与」(ボーナス)が払われる場合がほとんど。
これも各従業員の生産性に大きく影響を及ぼします。
毎月の給料ではなかなか余裕資金が作れないご家庭も多く、ボーナスを貯蓄に回しているという方も多いはず。
そんな意味でも「大切な収入」であったりするわけです。
さて、上記の2点は共通することがあります。
それは・・・・現従業員(在籍する人間)に支払うもの、ということ。
言い換えれば、支払うことによりその後の生産性に影響するものですね。
なくてはならない資金であるといえます。
さて、その一方で、実は生産性のないお金を従業員に支払う必要がある場合があります。
そうですね、表題の「退職金」です。
退職金なわけですから、もらった人間はその後基本的には企業では働きません。
(例外は嘱託または役員登用)ですので、退職金は「功労金の性格」「老後の生活資金の性格」を持っています
企業としては、長年貢献してくれた社員に報いたい、という意思表示です。
「だから今後も会社のために頑張ってね」というメッセージではない、ということです。
生産性の向上につながるものでなく、資金もまとまっているこの退職金。
実は中小零細企業では準備していないところが結構あります。
準備手段の卑近なところでは中小企業退職金共済(中退共)、税制適格退職年金(廃止決定済み)ではないでしょうか。
また確定拠出型年金を導入する企業もあります。
この年金制度に企業が掛け金を負担することで退職金準備のかわりになるのですが、運用指示するのが従業員自身であり、投資信託を使うため運用幅に差が生じることもあり二の足を踏む企業も多いのが現実です。
また、企業が契約者となり、生命保険(養老保険等)で準備することが多くの企業で導入されています。
これには「資金準備について企業主導で管理できる」点が上げられます。
企業は生ものなので、好不調に合わせ、メンテナンス出来る策が重宝がられているわけですね。
(退職金準備以外にも応用が利くこの手はMA加藤もオススメできます)
とにかく、準備していないで支払時期を迎えることは避けなければなりません。
資金準備ができないということは、資金繰り悪化が表面化したことを意味します。
借り入れ等資金調達の必要があります。
これがままならないと・・・・退職金倒産という話になりますね。
(退職金の延べ払いなどは出来ないものです)
一方で、企業側が準備できない理屈は理解できます。
- 準備したからと言って業績UPが見込めるわけではない。
- 今すぐに使うお金ではない。
- 他に運転資金・設備資金などの資金に使いたい。
こんなところです。
が、しかし、本当にそうは言ってられなくなってきたのが昨今です。
いよいよ長年勤めあげてくれた従業員さんなどの退職が始まってきたのです。
(また、近いうちに予定される状況になってきた)
とかく企業にとっては「後ろ向き」な資金ではありますが、だからこそ目を向けないでいるとインパクトの強いリスク資金となってしまうのです。
今からでも遅くはありませんので、各企業確認した方がいいですね。
口約束について

2007.07.15 口約束について
ビジネス上では、言った言わないで争われることが多々あります。
その最たるものが「裁判」でしょう。
事実認定をしたしない、といったことをそれぞれの側の理屈で正当化するわけ。
(光市の母子殺人事件などでイメージがわきます)
またミートホープ社の偽装ミンチ事件でも、「消費者が悪い云々・・・」などと、浅はかな社長が口を滑らせていました。
上記の2例については、事が大きいので、ここで書くまでもなく当局や司法が結論を出すのでしょうが・・・
少し話が逸れましたが・・・
我々が遭遇する仕事の場面では「裁判ざた」になることは少ないですが、かなり遺恨は残るものです。
その後の商取引にも影響が出たりします。
こんな事からも「口約束」からくる食い違いをビジネスでは生じさせない努力が必要。
基本は全て・・・「契約」が基本であるわけです。
仕事を受ける場合、まずは「契約書」。
これを意識していないといけません。
「口約束が一番危険だ」という認識が必要なのです。
私が相談を受けるケースで意外に多いのが、この「口約束がもとのトラブル」。
口約束では後に何も残りませんし、争うことはいくらでも出来ます。
しかし、結果は見えているんですね。
どういうことかと言うと・・・
口約束から争いになった場合、勝敗はすでに争いの前から決しています。
争う時点で勢力が強い方が、理屈抜きに正当化されてしまうのです。
チカラ技ですね・・・
だからこそ、中小零細企業では契約書を取り交わす癖が必要なのです。
MA加藤も銀行融資担当時代には、この憂き目に会った経営者を何件も見てきました。
そういう経営者に限って、「以前からの信用で契約書など交わさなかった」だとか「いまさら言えない」だとか仰っていました。
しかし実は、作成が面倒であったり、タイミングを逃したりしたせいでそうなってしまった、と言う場合もあるんです・・・
以上のように、ビジネス上の「口約束」は勢力を持つ側にとっては「都合の良いもの」であり、そうでない側には「都合の悪いもの」であるわけです。
金融機関への融資打診においてもその辺は大事。
例えば短期運転資金の申込の際に、融資担当者から「資金使途」を尋ねられるのですが・・・
「買掛金決済資金」や「仕入れ資金」等についての返済財源としては、「売掛金の回収」などが一般的です。
その際、どの売掛金の回収にて弁済するのか?が明示される必要があります。
よく言う、「引き当て」ですね。
「この資金が入ったらそれで弁済します」というものですから、融資担当者もそれなりの資料を求めてきます。
建設業であれば施主からの代金回収、請負業であれば請負先からの支払い、ということになります。
前者のような場合には「契約書」がある場合が多いものの、後者の場合には無い場合がチラホラです。
すなわち、下請け(孫請け)のような場合、後者が多い。
そして実際に資料が調わず、金融機関に短期運転資金を調達に行った折に、担当者から皮肉られてしまう結果になるのです。
「お宅は、まさか口約束で仕事をしているのですか・・・?」、こんな感じ。
その「まさか」が実は日常茶飯事・・・
とまぁ、これは資金調達しようとした際に障害となることを書きましたが、それ以前に、「契約(書)」を交わさず仕事を受けること自体がその企業に大きなリスクを背負わせることに気づかなければいけません。
売掛金が回収できず焦げ付いた場合、どうでしょう?
まず口約束では何も回収できません、というか債権者になることも下手したら出来なくなります。
証拠が無いわけですから・・・・
果たして、その企業は売り掛け先に対しどの程度の信用を感じていたのでしょう?
ここが問題点となりますし、経営上の大きな意思決定となるのです。
「相手を信用して掛け売りで商売する」とは何を意味するのでしょう・・・?
そうですね、答えは・・・「相手先に対し与信する、すなわち融資行為をおこなう」ことに等しいということなのです。
売り掛けとは・・・・「貸し」であることを忘れてはいけません。
それでも、貴方の企業は証拠無しに「信用貸し」を続けられるのでしょうか・・・?
ビジネス上では口約束は出来るだけ避けるべきと論じました。
では、国の体制はどうなのでしょうか・・・?
実はこういった部分は金融機関のみならず、政府もよく承知しています。
強い勢力が正しいと判断されてしまうこの世の中ですから、中小零細企業(下請け等)に対し、指南しています。
それが中小企業庁から発表されている、このガイドライン。
(ここでは「望ましくない取引慣行」と記載されていることが多い)
国も景気底上げを狙いとして、その辺りにも手当をしています。
なお、上記は中小企業庁のものですが、別の観点からも頭に入れておいた方が良い資料もご案内します。
こちらはちょっと堅苦しいかもしれませんが、法律上の問題。
ご覧になれば判りますが、中小零細企業(下請け)保護のための有意義な法律の変更点が明示されていますね。
一読しておくことをお勧めします。
中小企業庁のガイドライン・下請代金支払遅延等防止法等々、「それでも実際はそうはいかないんだ」とおっしゃる経営者も多いのが現実。
『仕事がこなくなったら困る』という潜在意識があるわけです。
すなわち、どのように環境を整備しても効果には限りが出てしまう・・・
もっともっと大事なのは「自社が動き出す」ことなんですね。
自らが動き出してこそ、望まれない取引慣行から脱することが出来るのでしょう。
言葉は不適切かもしれませんが、いつまでも周りや環境のせいにして「・・・・だから」と責任転嫁のようなスタンスでは、結局は上手くいかないのではないか、と感じます。
以上、ここに書きましたことを基に、ぜひ精力的に取引に臨んでもらいたいと思います。
役員退職金が否認される?

2007.05.09 役員退職金が否認される?
本年3月の税制改正で「役員の勇退(退職)の見解」に変更が出ました。
さて、どのあたりでしょうか・・・?
それは・・・「その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」という実質基準が加えられたのです
これはすなわち「実質上、引き続きその会社の経営に睨みを効かしている場合、退職とは認められなくなる」ということ。
例えば・・・
「代表者を退き、形式上会長(非常勤)になった(給与は70%減った)」という場合、従来ならば「退職」と見て良かったものです。
が、しかし・・・
息子が代表者となったものの、結局、実質上は会長(父親)が睨みを効かせている、という場合は「退職」として正式に認められなくなったのです。
2006年10月25日の大阪高裁判決でこういう状況の「分掌変更(もしくは退職)」は実態と伴わないと判示されてしまいました。
さて、そこで問題になるのが・・・
「役員退職金」にしても実情に合ったものでないと、退職金としての損金計上を否認される公算が圧倒的に高くなったわけです。
もともと役員退職金については「利益操作」の温床との認識があるものですから、その辺りを確かにしておこうということなのでしょう。
今後、役員の勇退(退職)金を出そうとしている企業については、「実態的に見てどうか?」の判断をよーくすべきですね。
ありがちなのは「監査役になった」とか「相談役に就任した」として退職金を払った場合。
実質上の判断が出来ないと、形式上は認められても否認されます。決算期間近に退職金を支給した・・という場合に、後に否認ということですと、企業にとってはオオゴトになるはずですよね・・・
注意しておかなければいけません。
むろん、「経営から完全に外れた」という実態があればなにも恐れることはないですから、安心してください。
すなわち、特に「分掌変更」の際に退職金を支給する時には要注意、ということです。
決算と赤字

2007.3.10 決算と赤字
日本の企業の約20%がこの3月に決算を迎えます。
多いですね・・・さすがに。
期末を迎えるにあたっては、どーしても業績が気になります。
- 思いの外、業績が良い会社
- 予算を消化できないで困っている会社
- 黒字なのに資金繰りがキツい会社
いろいろではないでしょうか・・・?
ここではその多くが悩む「赤字」ということを考えてみようかと思います。
赤字経営ではもちろん「正解」とは言えません。
何が悪かったのか?何が足りなかったのか?
多方面から分析し、評価し、今後への対策を打つことが必要になります。
当たり前です・・・
がしかし、「赤字」だけでは会社の倒産に直結するということではありません。
「赤字」でも事業の継続は可能ですよね・・?
どうしてでしょう・・・?
そうです、「資金繰り」が破綻しなければ会社は潰れません。
すなわち単純に「赤字」=「資金繰り破綻」ではないのです。
もちろん経常的な赤字体質であれば、・・・倒産でしょう。
赤字の判断には「一過性」のものか?「経常的」なものか?の判断が重要です。
では、その「経常的な赤字」とは何をもって判断するか・・・?
正解は・・・決算書(損益計算書)の「営業損益」欄
ここが連年に渡ってマイナスであると、「経常的な赤字」であり、完全なる赤字体質ということです。
最終的に、営業外の損益や特別の損益などで「赤字」を脱却していたとしても、本業の体質は変更は出来ません。
商売をしていて儲かっているのか?の判断は、まずはこの「営業損益」欄で確認しましょう。
(よく「経常損益」といわれますが、むしろ「営業損益」を優先しましょう)
この段階で「損失」が多いのは、はっきり言ってお勧めできません・・・
(金融機関もあからさまに嫌います)
一方で「経費項目で調整しているからやむを得ない」と言う方も大勢います。
しかし、それはどうでしょうか・・・?
細かい論議を省略して書きますと、それも「間違い」ではないか、と感じます。
会社としてその姿が「正しい」かと言えば、・・・・?
無理やり赤字にすることで、得られるものは何でしょうか・・・?
おそらく「その会社以外の損得勘定」に視点がいっているのではありませんか?
いや、きっとそのはずです。
私が今回話題にしている「赤字」とは、まさにこのあたりをどう捉えるか?ということです。
「営業をする価値(意味)があるかどうか?」の判断をしなければいけない、ということです。
冒頭の内容に戻りますが、こんな体質でも「資金調達」(借り入れなど)の先があれば、資金繰りは破綻はしません。
潰れない、ということです。
とはいえ、「潰れないからOK」ではなく、「営業する価値(意味)」からすれば「?」が付くわけです。
数字上や都合上ではなく、その会社を立ち上げた当時の「企業理念」に照らし合わせて、もう一度深く考える必要があるということではないでしょうか・・・
経営者としては重要な経営判断です。
不二家の不祥事について

2007.01.28 不二家の不祥事について
「人の口に入る物については、よほど慎重にならないといけない」と感じます。
今回の不二家の不祥事は消費期限切れの牛乳を使用したことが発端で、解れた糸がどんどん長くなるように、次から次へとアラが出てきました。
思い出すのは「雪印乳業」の事件ですね。
あの時も、出だしのニュースに火がついて、気がついたときは「私は寝てないんだ!」という声とともに、地獄へ落ちてしまいました・・・
さて、今回はどうなるのでしょう。
そもそも出だしのニュースとは、その全容が明らかになっていない段階で流れるものです。
企業はその初期の対応でボタンを掛け違えると、一気にその悪影響が出ます。
こういったセンシティブな部分の対応を「危機管理」といいます。
今回は社長以下が、まずは現場に「擦り付け」をした形ですね。
さらに発表を繁忙期(クリスマス商戦)を過ぎたところまで引っ張ったことが明らかになっています。
上記二点を受けて、マスコミ他が「噛み付いて」きたわけです。
残念ながら、「雪印乳業」での失敗が教訓にならなかった・・・
結局は社長が「辞意」を表明することとなりました。
「不二家」といえば「ペコちゃん」ですね。
私も子供が小さいころは、「クリスマスイブにケーキを閉店間際に駆け込んで買った」記憶が何度かあります。
確かにおいしかったし、「不二家のケーキ」といえば、何か違うような気になりました。
ブランド物を買ったという気持ちです。
現在では口にいれる機会は減りましたが、やはり残念です。
少し話が逸れましたが、なぜこのように「初期の危機管理」でこうも失敗してしまうのでしょう。
「雪印」も「不二家」もその点では同じ。
「動転していること」は紛れもない事実ですよね、こういう場合。
「事実を突き止めてから発表しよう、事実のみを公表しよう」という気持ちが強すぎるのです。
それは間違ったことではありませんし、大事なことです。
がしかし、こういう場合、「スピード」が重要なのです。
そしてそのスピードは「トップ」にこそ求められるわけです。
「いや、早いじゃないか、もう辞意を表明したぞ!」・・・ではないのです。
辞意など事態が収拾してからで十分ではないでしょうか?
先頭に立ち、「事実究明云々・・・」ではなく、企業として、そして社会的責任を負っている身として、謝罪に徹しなければいけません。
「言い訳」は後でかまわない。十分すぎるほど要求されるから。
「消費者への誠意ある謝罪」が伝わらないうちに、他の事に走りすぎているから、こう後手にまわされるんです。
こういうケースでは、とにかく謝って、謝って、そしてそれでも謝罪して認めてもらうことです。
さらっと「ごめんなさい」をするからこそ、とことんまで痛めつけられるんです。
一流になればなるほど「謝れない」、という現実が見て取れます。
画面上でヒョコンと謝っていても、伝わらないのです。
これが真実ではないでしょうか・・・?
今、一族で築き上げた巨大企業が、現場のミスで崩れようとしています。
さながら「首と腰の折り曲げ方が少なかった」ことで、最悪の結果になりそうになっています。
我々中小零細企業も不二家を反面教師としなければいけません・・・
担保について

2007.01.06 担保について
先日私の元へ一件の相談がありました。
「加藤さん、銀行で融資を受けたいんだ、土地担保で」
こういう相談です。
上記のままでは融資を受かられるかどうかなど、判断はできません。
まずは「担保があれば融資を受けられる」・・・・これは「大きな間違い」です。
さらに「何のためにお金が必要なのか」が明確であることが必要です。
事業などを経営している方々は、とかく錯覚してしまう部分です。
「担保」というのは万が一返済が不可能な場合、それらを換価して返済に充てるためのものですね。
「ならば、担保があればOKじゃないか」
・・・そうではないのです。
金融機関は、はなから返済できない融資などは請け負ってくれません。
(担保処分もそうそう容易ではありまえせん)
そもそも金融機関とは、融資を行い順調に返済いただくことで、その利息を収益とする訳ですよね?
仮に1,000万円の融資を受けるにあたって、1,000万円の担保があってもOKというわけにはいきません。
肝心なのは、あくまで「債務者の返済能力」上記の例でいけば、1,000万円の融資を返済するのに毎月150,000円の返済だとすると、これが「毎月順調に返済されるかどうか?」ということが問題なのです。
「担保」というのは・・・
「債務の不履行に備えて債権者に預け、債務弁済の手段に供されるもの」なのです。
『融資を受ける際にその可否判断に使われるもの』とは必ずしも言い切れませんので注意。
極端に言えば1,000万円の融資を受けるにあたっては正直幾らでも構わないわけ。
・・・こう書きますと勘違いされやすいのですが、あくまでも融資の判断見込みに「担保」を組み込んでは失敗が多いということを、ここでは言いたいのです。
このあたり、ご理解いただけるでしょうか?
この理屈が腑に落ちない、という方は、前時代の「担保優先主義」の融資を重ねてこられた方々だと思います。
「担保はあくまで担保」、もっと言えば「金融機関にとっては債務を履行してもらうための牽制手段」という感覚を持たないといけません。
厳密に言えば、確かにある程度担保評価によって融資判断がなされるのですが、それに期待しすぎてはいけません。
金融機関での融資審査のスタンスは昔とは確実に変わってきています。
「資産」<「実力」(返済能力)なのですね。
ということは・・・
融資の打診などで「担保、担保」と自ら先に出す方ほど、逆に「怪しまれる元」というわけです・・・
お金と現金の違い

2006.12.15 お金と現金の違い
先日MAアドバイザリーご契約先の社長とお話しをしました。
「資金繰り」についてのことです。
この会社は創業より業績が常に伸びている「黒字企業」
そしてこれからも成長が見込める企業です。
しかし、残念ながら業歴が浅く「資金調達面」では少し苦労があります。
経営者であればよーく分かることですが、「業績(決算)」と「資金繰り」は合致しません。
すなわち・・・「黒字」=「資金が潤沢にある」ということではないのですね。
資金繰りとは、あくまで「現金」に視点を合わせたものです。
そこには極端に言えば「黒字・赤字」の概念は存在しません。
「黒字だろうが資金繰りの悪い会社」もあるわけ。
上記の会社でも同様でした。
・・・・・ここでは詳細は省略・・・・
では、なぜこのような現象が起きるのか・・・?
それは「交換取引が同時ではない」ということです。
簡単に言えば「物々交換(モノとモノ)」であればこのような現象が存在しません。
しかしながら、「商売」はそれでは成り立ちませんね。
原始時代のように、作物を獲物で交換するというわけにはいきません。
(車を買うのに、お米で支払うということは出来ませんね)
そこには何が存在するかというと・・・
「お金」です。
そう、とある時に「お金」という「対価を表す共通の存在」が現れたのです。
これにより、モノが激しく活発に動くことになり、現在に至っているのです・・・
少し話しが逸れましたが、このように「お金」というものは大変都合が良いものですね。
何においても「価値」が判るからです。
なので、会社経営の場合、決算書などを見ますと・・・・
一年間のお金に換算した「売上」という価値の総額。
また、お金に換算した「売掛金」「在庫」なども共通単位で表示されます。
これならば「見やすい」ということです。
が、これがしかしクセモノなのですね。
そこに10,000,000円と記載があれば現金10,000,000円があるものだと勘違いするのですね。
例えば、在庫などが良い例です。
これであらかたの人は「焦点」(ピント)が合わなくなるんですね。
いいですか、上記の例でいけば・・・
「売れたら」10,000,000円の価値がある商品というだけのこと、なんです。
従って「売れなければお金(現金)にならない」訳。
在庫=お金ではなく、在庫=見込みのお金なのですね。
今まではそれでも「貸借対照表」や「損益計算書」を見るに付け、その意識が飛んでしまっていたのです。
「黒字なのに資金が足りない」だとか「常に資金不足」だと言うのには、こういった「価値」を単純にお金に換算してしまう癖があるからなのです。
そうして「お金があるという間違った錯覚」に気がつかないのです。
こうした錯覚から現実に引き戻しをしてくれるのが、そう「資金繰り表」であり「キャッシュフロー計算書」なのですね。
私は「資金繰り表」の重要性を口癖のように言います。
その度に経営者さんの多くは「めんどくさそうな顔」をします。
確かに面倒なことかも知れません。
「頭の中での勘」に頼る経営者もいます。
(この手の経営者さんは確かに勘がいいので、さらに困ります)
現実問題として、商売に「お金(現金)」はつきものです。
がしかし、その「お金」は実際の現金を指す場合と、「現金に換算した場合の価値」を指す場合があるということを理解しないといけません。
ここで勘違いした企業は、その修復に大きな負担を強いられる事になるというわけです。
「お金というのは大変便利なものであるとともに、錯覚しやすいものだ」ということを忘れてはなりません。
「現金」とはあくまで単純に「そこにあるお金」なのですね・・・
減価償却見直しの効果

2006.11.28 減価償却見直しの効果
そもそも「減価償却」なんて「黒字会社の問題だ!」・・・・
そうかもしれません、「損金」についての制度ですから。
が、しかし現在黒字でなくても、また業績が上がるかもしれません。
そんな時に「知らなかった」では良くありませんので、ぜひご一読を。
今回本格見直しの「減価償却制度」ですが、11/26付の日本経済新聞に分かりやすい記事が掲載されていました。
サンデーニッケイの「視点」というコーナーです。
「減価償却制度の見直し」というのがそれ。(詳しくは日本経済新聞をお読みください・・・)
- ステップ1、そもそもは
(現行制度について) - ステップ2、どうして
(見直しの内容) - ステップ3、これからは
(その効果)
という分かりやすい構成です。
これですべてとは言い切れませんが、少なくとも経営者としてこのレベルは掴んでおきたい部分だと思います。
2007年税制改正の柱となる内容ですね。
さて、この結果が中小零細企業にどのような影響を及ぼすか・・・?
ここが問題です。
中小零細企業では例えば「航空機」などを所有することなどないのですから、身近なところで考えたいところです。
まずは、実質「損金算入」の枠が広まることです。
・・・ということは確かに「赤字」では意味がないことです。
実際、黒字企業の「利益が抑えられる」という効果がほとんどで、これによって黒字企業が負担する「法人税」が軽減されるのです。
特に「製造業」においては「設備投資」が進むことで、「景気がよくなる」という現象がじわりじわりと現れるととが予想されます。
ところが、中小零細企業ではその恩恵を受けるにはまだまだ時間がかかるのです。
そうですね、まずはいいとこ取りは「大企業」からと決まっています。
なので表現とすれば、「じわりじわり」と言ったところでしょう。
がしかし、目先の施策よりもこういった「ボディーブロー」のような施策は効果が出るのに時間がかかる分だけ、その効果の継続も長いものです。
すなわち短期的視点に立たないでいれば効果が期待できるというものです。
やがて、この効果は「製造業(関連)」から「小売り・サービス業」へと広がるはずです。
(残念ながら中小零細企業は、必ず貧乏くじを掴まされる構造です)
ただしです、「景気」というのは案外「感情的」な部分を多くはらむものです。
大企業にとって「美味しい材料」が整ってくる世の中は「明るさ」が出てきます。実はこの「明るさ」が重要です。
中小零細企業にとっては「掴み所がない明るさ」でも好材料になるんですね、これが。
やはり「大企業頼み」と言ったところでしょうか・・・
この恣意的につくられた(?)ムードによって、中小零細企業の景気(感情)はやがて上がるのです。
「親が明るい子供は明るい」
「笑顔が絶えない家庭にはよい子が育つ」
このように「人間の人格形成」などにも同様な意味合いの言葉が良くありますよね。
そうです、意味など無くてもそれが事実なんですから・・・
企業の社会構造でも、ある意味一緒・・・
今回の制度改正は私は中小零細企業にとっては、実はこんな風な改正ではないか、と受け止めています。
中小零細企業のM&A

2006.11.14 「中小零細企業のM&A」
明星食品と外資スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド、牛角でお馴染みのレックスHDのMBO(経営陣による企業買収)、はたまたホンダが子会社にする目的で八千代工業にたいしTOBを行うなど、実にこのところM&A全体が表面に出てきたように感じます。
今年、日本が従来のデフレ脱却をしてからは、「動き」が見えてきた感があります。
躍動感が出るということは、私も重要だと感じます。
無論これは上場企業など、いわゆる大企業の分野ですが・・・・
では、中小零細企業の現状はどうなのでしょう・・・?
実は、今現状では大企業ほどM&Aは目立たない状況です。
やはり物事は「上から下へ」が基本なのでしょうかね。
正直なところで言えば、まだまだ「大企業(親企業)任せ」といった部分が大多数を占めています。
なので、良い意味でその余波が来るのはもう少し先になるのではないか、というのが私の見方ですね。
その上で、中小零細企業なりのM&Aを展開していくことになるでしょう。
当然、中小零細企業なのですから「上場云々」ということも考えの外の場合がほとんどです。
これからの中小零細企業間では、その丈に合わせたM&Aが展開されるのではないかと思います。
例えば・・・
「事業承継(跡継ぎ)に関わるM&A」
「経営者一身専属の企業の精算のためのM&A」
「営業権買い取りをすることで規模の拡大を図るM&A」
などが、代表的なところになると感じます。
そしてこの時に何が一番大事なこととなるか・・・?
上場企業では・・・「株価」ですね。
一目で判るので、言ってみればむしろ簡単なのです。
中小企業では・・・「株価」とも限りません。
ここが非上場が故の悩ましいところでもありますね。
では何か・・・?
それは会社の「実体力」、すなわち「資産(資源)」ということです。
「どれだけの経営資源を持っているか?」、がポイントであることは間違いありません。
・・・・ということは「人」「物」「金」「情報」が重要だと言うことです。
これら経営資源が会社の「値うち」の元になることを頭に置くべきです。
(経営資源については後日詳しく書こうと思います)
「決算書」を筆頭にする財務の問題にあわせ、さらにマンパワー・技術力・知的財産等々が非常に大事です。
このあたりの価値観で「中小零細企業の値段」も決まっていくことになります。
なお、これらは「決算書」のように一覧で確認することが困難なものばかりです。
しかし、中小零細企業にとってはとても大切な資源になるわけです。
「自社ではマンパワー・技術力・知的財産等々がどの程度のものか?」といったことを客観的に考えてみるのも経営判断の良い材料になると思います。
M&A前提ではなくても、例えば大幅な取引条件の決定時などには「見直す」ことが肝要です。
決算時はどうしても「数字」ばかりに目が行きがち。
そうでないときには、ぜひその他の経営資源の見直しをしてみましょう。
このあたりから経営のヒントが生まれるかもしれません。
お役立ち情報

2006.10.31 「金庫破り」
MAアドバイザリーのお客様の事務所に「金庫破り」が入りました。
本日お伺いしたところ、玄関のガラスドアの取っ手付近が無惨に割れています。
(実況感ありあり)
聞いてみると今朝従業員が来たところ、表門もこじ開けられ、ドアは壊され、金庫ごと盗まれてしまったそうです・・・
金庫は100㎝×60㎝×60㎝というので、なかなかに大きい。
実際金庫は重たいですよね。
おそらく100キロはゆうに超している、いやもっとか・・・
間違いなく独りではまず無理、数人がかりで持つのもやっとでしょう。
犯人達は二階にある事務所から持ち出し、階段で金庫をガランガランと落としたようで、階段も壊れていました。
いやぁ、凄い大胆な犯行です。
しかもセキュリティーカメラがあるのを壊して侵入。
時間にして約6分以内の犯行のようです。
運悪くここの事業所は玄関近くに井戸が湧き出ており、その水音でこれらの犯行の音が隠されてしまったようです。
ここまで大胆な犯行というのは、日本人では難しいのでは・・・?とも感じました。
確かに最近は少なくなりましたが、ATMごとユンボでもぎ取るという事件も多発しましたが、そこまでではないにしろ、凄いですね・・・
で、盗まれたものとは・・・・
これが幸い、小口現金数万円と通帳数十冊、その他書類がほとんどだったそうです。
これは救いでしたね。
実印も盗まれておらず、実務上も混乱が少なかったようです。
「招かれざる客」も実利は少なかったわけです。
こういった「事務所荒らし」はときどき発生しますね。
普段からの「備え」が必要だと感じました。
その対策は・・・
そのリスク度合いから考えることが重要。
泥棒はしょっちゅう来るのか?
被害想定額はどうなのか?
どこまで対策コストをかけるか?
その中で最適なものを選択し、対処することになります。
- 監視カメラなどの強化等・・・・「軽減」
- 盗難に対する保険・・・・・・・・・「転嫁」
- 金庫などを置かない・・・・・・・・「回避」
- まるっきり度外視・・・・・・・・・・「放置」
どれが不正解というものでもありません。
何が最適か?を判断することになります。
この事業先は「軽減」、セキュリティー強化を選択したようです。
(これはこれで正解ですね)
このように「将来起きるやもしれない不測の事態に備える」ことを「リスクマネジメント」といいます。
これもその一つであることが判るかと思います。
「被害を想定し、事前に手を打つ」
これは出来そうでなかなか出来ないものです。
ここの会社のように「被害が少なかった」ですまされる場合は良しとして、被害想定額が大きい事業先はぜひ一考の価値もありそうです。
気をつけましょう!
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
社外相談役としての経営判断・意思決定のアドバイザリーのご利用や、資金調達セミナー・経営セミナー等の講師依頼をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

